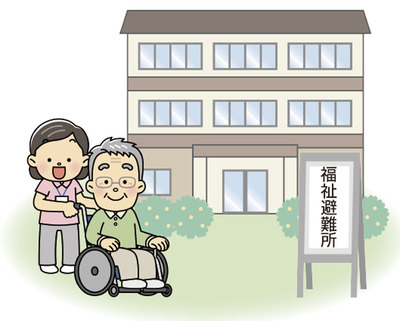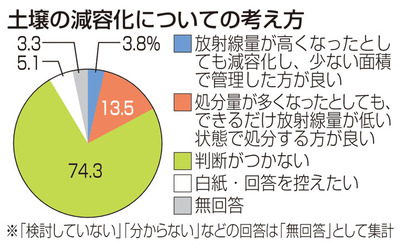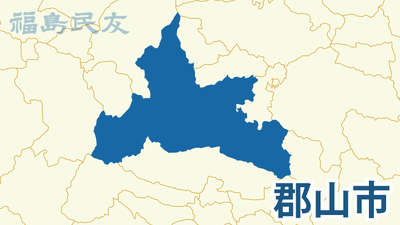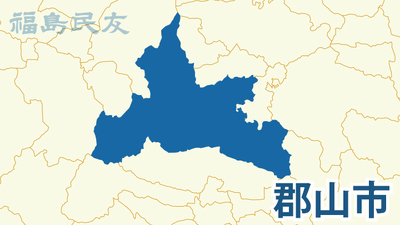東日本大震災と原発事故をきっかけに、避難所の姿は大きく変わりました。当時は毛布を敷いただけの環境で、多くの人が不自由な生活を強いられました。特に高齢者や障害のある人、持病を抱える人にとっては、一般の避難所での生活が大きな負担となり、健康の悪化につながる例も少なくありませんでした。こうした経験から、要配慮者を守る仕組みとして「福祉避難所」が整備されてきました。 福祉避難所の必要性が広く認識されるよ...
この記事は会員専用記事です
残り509文字(全文709文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。