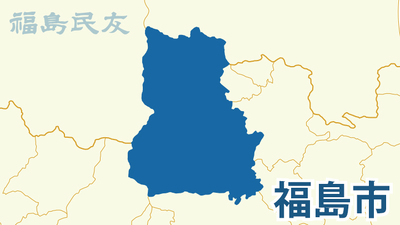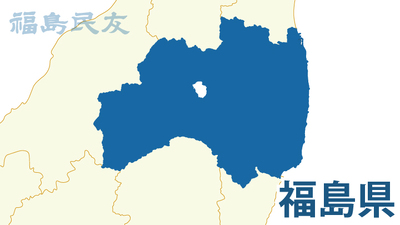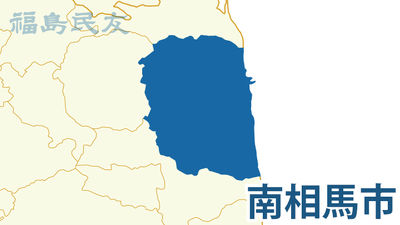「こころとあたまの、深呼吸。」を標語とした読書週間が11月9日まで展開されている。普段は読書に無縁という人も、ぜひ本に触れる時間をつくってほしい。
文学紹介者として本の執筆や編集に関わる頭木弘樹さんは大学時代に難病にかかった。もう思い描いていた将来が生きられないと悲観していたとき、カフカの本に「生きることは、たえずわき道にそれていくことだ」とあるのを読み、言葉に寄り添ってもらっているような思いがした経験があるという(「絶望読書」飛鳥新社)。
本はこれまで多くの人が悩んだり、調べたりしたことが集まってできている。それを読むことで同じ苦しみや疑問に直面したとき、人は何を感じて、どう考えたのかをたどることができる。本好きの中には、本に自分がもやもやと抱いている感情を言い当てたかのような表現を見つけたり、救われる思いをしたりした人がいる。
読書離れを巡っては、子ども、若者に焦点が当たりがちだ。しかし、社会生活を送る中でさまざまな悩みや課題に直面するのは、大人も子どもと何ら変わりはない。社会が多様化する中でこそ、本に収められた英知は、私たちの未来や日々の生活をより良いものとするための羅針盤として、大人にとってもますます重要だ。
文化庁の国語に関する世論調査によると、「(1カ月に本を1冊も)読まない」と答えた人が全ての年代で6割を超えた。読まない、読む量が減っている理由は「情報機器(携帯電話、スマートフォンなど)で時間が取られる」(43・6%)が最も多かった。
スマートフォンなどから得られる情報量は人工知能(AI)の発達もあって格段に増え、利便性は高まっている。しかし、目的に沿って何を調べるかを考えたり、検索などで必要な情報にたどり着き、利用したりするには一定の知識が必要となる。専門家が必要な情報を精査、解説している本を読むことで探すべき情報や、その情報の見方は鍛えられる。
スマホなどから得る情報の質を高め、活用するためにも本は有用であることを知っておきたい。
何を読めばよいのか分からないという人は、図書館や書店に行ってみてほしい。書棚を巡れば、何冊かは興味の湧く本が見つかるだろう。司書や店員に相談すると、目的に沿った本を教えてくれる。
かつて読んだ本を再読してみることも勧めたい。書いてある内容は変わらないが、読む側の現状や心境の変化で読み取れるメッセージが違ってくることがある。