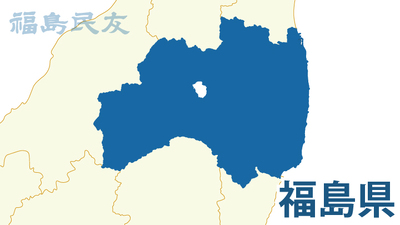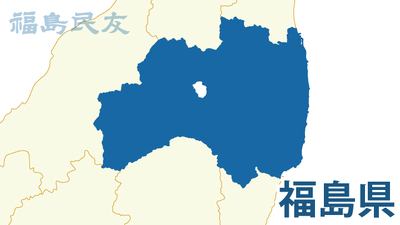東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)が、開館から5年を迎えた。震災と東京電力福島第1原発事故の教訓を伝える拠点として、これまで40万人を超える来館があった。震災から14年半が経過する中、来館者により深い学びを提供していくことが重要だ。
伝承館の来館者数は右肩上がりだったが、新型コロナウイルスの感染拡大が収まり、旅行先が多様化した昨年度は、初めて前年度を下回った。本年度は8月末現在で、過去最多の来館者だった2023年度に近い水準で推移している。伝承館の担当者は、7月にロシアを震源とする地震により太平洋側に津波警報が出て、防災への関心が高まった親子連れらの来館があったことが影響したとみている。
来館者数の回復傾向は、伝承館に「災害を学ぶ場」として一定の認知度があることを意味する。南海トラフ巨大地震などの発生が見込まれる状況で、防災の知識を得ることへのニーズは高い。伝承館は、震災の教訓を踏まえながら今後予想される災害をイメージし、それに備えるための知識が得られるような展示を充実させ、多くの来館につなげてもらいたい。
伝承館が現在、力を入れているのは11年に発生した震災を直接知らない世代である、中学生らへのアプローチだ。担当者が県内の中学校を巡って研修などでの来館を呼びかけているほか、来館前に展示内容について事前学習することができる中学生向けの教材を作り、ホームページでの無料公開を始めている。
事前学習の教材は、津波や原発事故の状況、避難生活中に亡くなった「震災関連死」が多いことなど、複合災害の多様な側面を簡潔にまとめている。教職員用には、どのように事前学習を進めると効果的なのかを示した指導書も作成した。伝承館は、これらの教材を使えば震災学習に取り組みやすくなることをアピールし、次世代への記憶の継承を進めてほしい。
伝承館は9月、福島民友新聞社との連携協定に基づき、石川町の石川義塾中で初の出前授業を行った。これまでに培った震災伝承のノウハウを生かし、外部での講座などを企画することも、震災を風化させない一つの手法だろう。
伝承館には、震災関連の資料の収集や保存の役割がある。震災当時、政策決定や避難受け入れなどに当たった行政や民間企業の担当者の中には、すでに定年退職を迎えた人もいる。貴重な体験を記録として残すため、それぞれの記憶が薄れる前に積極的な聞き取りを行うことも重要になっている。