【第3部・斎藤清<上>】描く衝動、版画の原点
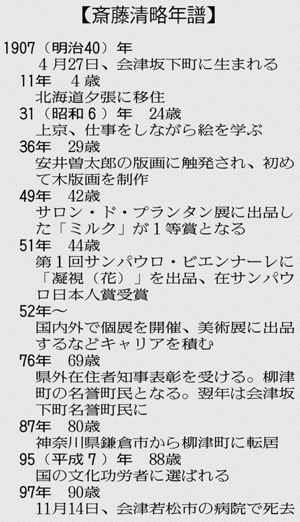
「描かずにはいられなかった」「何かを描いていれば心が落ち着いた」。描くことへの衝動に駆られた少年は、世界的芸術家になった。会津坂下町に生まれた版画家、斎藤清(1907~97年)である。
会津描き続け
「おしゃれでモダン。時代を超えた、古びない魅力がある」。県立美術館(福島市)の学芸員、増渕鏡子さんは斎藤の作品をこう評する。斎藤は1984(昭和59)年の同館開館を前に、よりすぐりの自作約300点を施設に寄贈するなど縁が深い。それだけに、斎藤は「別格」というほど大切な作家だという。
代表作「会津の冬」をはじめ、斎藤は故郷を描き続けた。そんな斎藤の大きな仕事の一つに、増渕さんは「会津の『雪深い、人情味ある古里』といったイメージの形成」を挙げる。「このイメージは戦後につくられたもので、必ずしも昔からあったわけではない」と増渕さん。斎藤を「戦後福島のアイデンティティーの確立に一役買ってくれた、県民にとって思い入れの強い作家」と話す。
出発点は油絵
版画で知られる斎藤だが、出発点は油絵だった。「とにかく描きたい」。突き上げるような感情はあるものの、描き方も分からず初めは水彩絵の具に食用油を混ぜて描いたという。一時師事した人物はいたが、ほぼ独学だった。それでも、次第に公募展での入選を重ねるようになる。
29歳で版画と出合った。東京・銀座で偶然目にした洋画家、安井曽太郎の版画に立ち尽くすほどの衝撃を受けたという斎藤。増渕さんは「伝統的な木版画を現代風にやり遂げた安井の作品に、新鮮さを感じたのでは」とみる。斎藤はすぐさま手探りで最初の木版画「少女」を制作。版画でも油絵の絵肌を持つ作品ができることを知り、のめり込んでいったという。
木版画「凝視(花)」は斎藤を国際的作家へと押し上げた作品だ。木目を生かした質感、横向きの人物に目、涙、花といったイメージが簡素な形で表現されている。この作品で斎藤は51年、第1回サンパウロ・ビエンナーレ在サンパウロ日本人賞を受賞。戦後、日本人初の国際展での受賞という快挙だったが、なんと本人は出品したことすら忘れていたという。これを機に国内外で個展を開催、美術展での受賞を重ねるなど、大家への階段を上っていく。
温かな晩年
晩年は妻の文(ふみ)と、柳津町のいとこ、渡部ヨシノ一家の元で暮らした。「毎日が楽しかった。食事の時は私がおじちゃんの隣と決まっていました」と話すのは、ヨシノの次女久子さん(64)=本宮市。「真面目で優しく、自分に厳しい。こんな心のきれいな人がいるだろうか」と「おじちゃん」の人柄を懐かしむ。
スケッチに行く時はヨシノが用意した大好きなコーヒーとサンドイッチ、クッキーを持参。日も暮れようとするある雪の日、心配したヨシノがスケッチ中の斎藤のところに行くと「ヨシノ! 眼鏡!」。かばんを捜してもない。眼鏡は叫んだ本人がかけていた―。久子さんはそんな日常の一こまを語り「母は(斎藤と)いとこながらきょうだい以上の不思議な絆を感じていたそうです」と振り返る。
「チャコ、おじちゃん、若い頃は華やかだったんだよ」。自慢を嫌う斎藤が、ふと語りかけてきたことがあった。久子さんは「田舎の温かな家庭で過ごす中で、かつての自負が顔をのぞかせたのかな」と言う。父が商売で失敗、4歳で北海道夕張に渡った。母とは12歳で死別した。「描きたい」。その一心で身を立てた苦労人は老境に至り、安住の地で何を思ったのだろう。
斎藤は創作をしばしば「戦い」と表現した。その意味で、戦いは生涯続いたといえる。長きにわたる画業は、描かずにはいられない業を背負った者の、格闘の軌跡にほかならなかった。(一部敬称略、高野裕樹)