【復興の道標・作業員-2】気ままな受診に疲弊 時間外来院や健康保険未加入
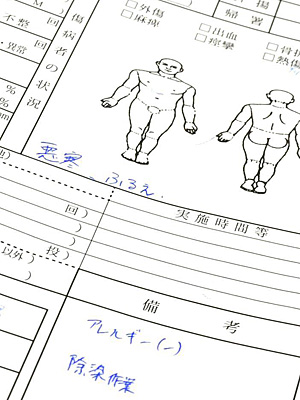
「お姉ちゃんはどこに住んでんの? ここらへん?」
昨年11月のある夜、広野町の高野病院に、県外から来ている40代ぐらいの男性作業員がひどく酔った様子で受診に来た。男性が救急室に入った後、事務の女性職員(45)が付き添いの男性に患者の住所を尋ねると、やはり酔った様子の男性が関西弁でそう聞き返してきた。「じゃあ本人に確認しますんで」と、女性は苦笑して会話を遮った。10月にも酔った作業員が来たことがあった。「最近多いなあ」
当初腹痛を訴えていた患者は点滴を拒否。特段の治療を受けなかった。「さあ、これから飲み直そうか」。病院を出るなり、患者がそのような言葉を口にしたのを、女性は聞いていた。
原発事故前は月1件あるかどうかの程度だった救急搬送や時間外受診が年間60件に増えた。除染作業員などの診察が目に見えて増えた。インフルエンザで救急車に乗って来た作業員がいたほか、「会社に病気だと伝えると仕事をなくす」と言って、あえて通常の診療時間外に診察に訪れる作業員もいた。
10月上旬のある夜、「福島に仕事をしに来た」という男性が救急車でやって来た。健康保険証を出そうとせず、治療が終わるといつの間にか、いなくなっていた。「具合が悪ければ明日、もう一度薬を出しますから」。そう伝えたが、その後姿は見せず、医療費は未払いのままだ。
増える時間外の来院
浜通りでは、事故当初放射線への不安から子育て世代の女性が多く避難したことで看護師が不足。一部病棟を閉鎖したまま診療を続けている病院が多い。人員不足の上、度々来院する作業員の問題が追い打ちを掛ける。
労災事故や重篤な病気の場合はできるだけ早期の来院が求められる一方で、軽症で時間外に来院したり、健康保険に加入していないなどのケースが病院を悩ませる。
「また『J』が来たよ」。相双のある病院の看護師らはいつしか、除染作業員を頭文字の「J」で呼び合うようになった。
「廃炉や除染に当たる会社でもしっかりした会社なら患者に上司が付き添い、名刺を置いていく。しかし、そうではない下請け会社があり、元請けの会社に改善を求めても末端まで周知されていない」。そう話す高野病院事務長の高野己保(みお)(48)は、職員の離職につながらないか心配している。「中には職員に暴言を浴びせる人もいる。職員が減って、患者は増えた事故後の現状で、これ以上職員にストレスを与えたくない」(文中敬称略)
(2016年1月8日付掲載)
- 【復興の道標・放射線教育】ママ考案「○×テスト」 相馬・中村二中で初授業
- 【復興の道標・放射線教育】学び続ける風土つくる 意欲に応える方策を
- 【復興の道標・放射線教育】教える側の意識が変化 福島モデル確立へ
- 【復興の道標・放射線教育】「なぜ学ぶか」が出発点 理解し伝える力に
- 【復興の道標・放射線教育】「放射能うつる」の誤解 学校外の連携模索
- 【復興の道標・放射線教育】安全性伝える知識必要 相馬農高生が実感
- 【復興の道標・放射線教育】子どもが学び家庭へ 測定検査で実践的活動
- 【復興の道標・識者の意見】立命館大准教授・開沼博氏 寝た子を起こすべき
- 【復興の道標・識者の意見】県国際交流員・ナオミオオヤ氏 ALTが情報発信
- 【復興の道標・番外編】理不尽に心痛める福島県民 教育・行政対応求める