女性中学校長、福島県5人 教育分野低迷...特に学校管理職比率

上智大の研究者らでつくる「地域からジェンダー平等研究会」が国際女性デー(8日)に合わせ公表した2023年の「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」では、各地域の政治、行政、教育、経済の4分野での男女平等度が示された。本県は教育分野が46位と低迷し、特に学校の管理職の女性比率が低かった。中学校長と副校長・教頭は全国最下位。学校の男女格差はそこで学ぶ子どもへの影響も懸念される。校長の女性の声と県教委の取り組み、教育社会学の専門家が指摘する改善のための方策をまとめた。
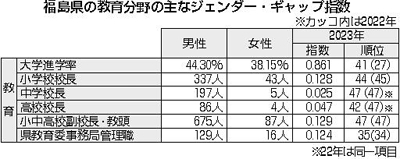
立場与えられることで、能力や資質に気付くことがある 原町二中校長・和田節子さん
「女性の中学校の校長が県内に5人しかいないと生徒に伝えると、『えーっ?』と驚かれるんです」。原町二中校長の和田節子さんは言う。
県内の市町村立中学校の女性管理職の割合(本年度)は4.4%。和田さんは、学校の女性の管理職が増えるために必要なこととして「教頭などへの昇任制度の改善、固定概念を変える、管理職自らが仕事の魅力を伝える」の3点を挙げる。
「管理職との巡り合わせがその教員の将来を左右する。しかしそういった『運任せ』ではなく、公平にチャンスが得られる仕組みが必要だ」。上司からステップアップの機会を与えられず、昇任試験のスタートラインに立てない女性がいるのかもしれない。そう考え、女性を育成する管理職側の気構えを共有する必要も指摘する。
管理職になるよう女性に勧めても断られることもある。理由は家事や育児のほかに、夫も教員の場合は「夫より先に昇進できない」ということも。「試験に受かったとしても『女性だから優遇されたんだろう』と言われたくない」との理由もあった。「もしかしたら管理職の魅力を伝えきれていないのかもしれない」と、管理職の仕事のやりがいを伝えていくことの大切さを感じている。
自身は教務主任時代、男性教頭が忙しさの中でもユーモアを持って職員室の要になっている姿を間近で見ていた。自分らしさを出してチームづくりをしている様子に「これでもいいんだ、自分もやれそうだな」と思うことができたという。「ロールモデルは性別を問わずどんなところにもいます」
本年度で定年退職する。生徒たちには「誰もが自分らしさを発揮したいし、らしさを発揮する相手を認めよう」と伝えてきた。女性の教員たちに向けても「立場や、やらなければいけないことを与えられることで、自分が気付かなかった能力や資質に気付くことがある。もっと自分の力を、管理職として発揮してほしい」と、呼び掛けている。
県教委が挑戦後押し 自宅から通える配置、ロールモデル発信
管理職への昇任試験を受ける女性教員が少ない理由について、県教委は、県土が広いため管理職として自宅から通えない遠方の学校に赴任することを敬遠している、女性管理職の手本(ロールモデル)が少なく不安に感じている、ことが主な要因とみている。
このため、県教委は市町村立学校の管理職は原則として自宅から通勤可能な配置にしているが、県立高はまだ導入しておらず、家族がいる場合は単身赴任での着任となるケースも想定される。
ロールモデルが少ないことの対応としては、本年度から県教委ホームページで「女性教職員活躍推進だより」の発信を始めた。校長を務めている女性や、管理職経験がある県教委勤務の女性教員に、昇任試験を受けたきっかけや、管理職の仕事のやりがい、大変だったことなどを聞き、女性教員を励ますメッセージをインタビュー形式で紹介。昇任試験にチャレンジする意欲を促そうと、8月の出願締め切り前の5、6、7月に発行したほか、新年度の人事異動を見据えて2月にも出した。
県教委によると新年度は教頭に就く女性が増える見込みといい、2025年度までに副校長・教頭15%(国の目標25%)、校長13%(同20%)とすることを目指している。
子どもが見る世界を変えていく 山形大学術研究院教授・河野銀子さん
学校長や副校長・教頭の男女比率の偏りを改善するためにはどんなことが必要なのか。山形大学術研究院教授(教育社会学・ジェンダー研究)の河野銀子さんに聞いた。
まず学校教育から
―都道府県版ジェンダーギャップ指数によると、本県は学校の管理職で女性比率が少ない。子どもにどんな影響があるか。
「結果を見ると福島県は教育以外のジェンダーギャップも大きい。教育界特有の問題ではなく、県全体の問題なのではないか。そうなると、みんなが通う学校での教育から変えていかないといけない。子どもは目の前にある世界が当たり前や自然のものと考える。学校の管理職に男性が多いなどの状況に接していると、それを普通と思う。そしてその『普通』ではない状況を『変だ』と思うようになる。そうなってしまったらジェンダー平等の社会にならない。だから積極的に、子どもが見る世界を変えていく必要がある。ジェンダーギャップが小さい県の子どもと、大きい県の子どもが見ている世界は大きな隔たりがある」
―校長や教頭に女性が少ない理由は。
「その仕事に魅力がないからだろう。だから、魅力をつくり、発信することが必要だ。女性に『やってみては?』と促す周囲の声掛けも重要で、声が掛かるかどうかで次の仕事が変わり、その積み重ねが経験の差となる。男女格差が大きい県は特に、管理職試験を受ける前の段階で女性が男性と違う扱いをされている可能性が高いだろう」
なぜ断るか考える
―管理職志望者を増やすためには。
「女性がなぜ断るのかを考えるべきだ。声掛けが男性ばかりになりがちならば仕事を割り当てる時に女性を必ず思い浮かべる、男女両方に促すなど工夫が必要だ。出産前や育休から復帰した女性に配慮のつもりで声を掛けないことも、10年後に男性との差になる。断られても『状況が変わったら考えて』と声を掛け続けてほしい」
―ほかに何が効果的か。
「育児休業から復帰した後のサポートと、管理職になる研修が受けやすくなる工夫、教職員向けのジェンダー研修だ。特にジェンダー研修は都道府県の男女共同参画の部署と協力して行っているところもあるが、ごくわずか。時代に合った知識や教員養成課程で学んでいないことを知るためにも研修が必要だ。世界と日本の状況と日本の課題を客観的に知ると、意識が変わっていくだろう」
―中学、高校は教員の女性自体が少ない。
「全国的に小学校や特別支援学校などは女性が約6割、受験を考える中学、高校になると3~4割と、学校段階が上がるほど減る構造的な問題がある。校種によって課題が異なり、中学・高校は女性教員を増やす努力も必要だ。昔は女性が働き続けられる仕事といえば教員だったが、今はワークライフバランスを重視した企業が増えた。黙っていても優秀な女性が教員になる時代は終わった。女性教員が活躍しやすい仕組みを作らないと女性がどんどん教育以外の分野に行ってしまう。加えて首都圏の教育委員会が女性の働きやすさをPRして地方の学生を勧誘している。若い人は勤務条件やキャリア形成に有利なところを積極的に選ぶ。地方は選ばれるように改善した方がいい」
かわの ぎんこ 武蔵大人文学部卒、上智大大学院教育学研究科博士課程修了。博士(社会学)。2014年から現職。編著書に「女性校長はなぜ増えないのか」(勁草書房)など。日本学術会議連携会員。
- 女性警察官初の所属長、福島県民を守るヒーローに 県警採用1期生
- 「力合わせ社会変える」 ソロプチフォーラム、選出100人心一つ
- 女性の輪...つながる街に 郡山で討論、異業種100人が目標宣言
- 福島県...政治、教育のジェンダー・ギャップ深刻 都道府県版指数
- 楽しく農業「女子会」設立 県北地方25人、研修会で栽培技術磨く
- 働き方、女性経営者が意見交わす 会津大開学30周年シンポ
- 女性リーダー阻む「偏見」 少ない事例...想像できず、福島で座談会
- 母と警部「両立」誇り 福島県警の女性警察官誕生から30年
- 「福島で働く」若手女性が意見 内堀知事に職業観や仕事への考え
- 筋の通った女性になって...孫娘に託した一冊、72歳祖母の思い届ける