福島県、語り部活動体系化 震災伝承仕組みづくり、人材育成へ
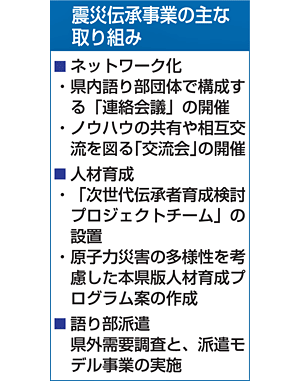
東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から11年が過ぎ、記憶と教訓の風化が課題となる中、県は新年度、「語り部」による伝承事業を強化する。それぞれ独自に活動している語り部団体のネットワーク化や、人材育成などが柱。語り部を巡る取り組みを体系的にまとめ、未曽有の大災害を長期にわたって伝承できる仕組みづくりを進める。
具体的には新年度、語り部団体が一堂に会し、活動を取り巻く現状や課題を共有する「連絡会議」や、語り部同士が互いの発表を聞きながら研さんを積む「交流会」を複数回開催する。団体間の横の連携を促しながら「伝える技術」の向上を図る。
県の施設の東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)など、県内の伝承施設には、県外から多くの来場者が訪れている。このため県は県外での需要調査を進めながらニーズを掘り起こし、将来的に語り部を県外に派遣できる体制を構築する。
また、学識経験者や語り部によるプロジェクトチームを設置した上で、原子力災害の多様性などを踏まえた本県版の人材育成プログラム案を作成。語り部団体とも共有し、プログラムに基づいた人材育成を展開してもらう。
語り部を巡っては、県内でさまざまな団体が活動しているが、団体間の連携や、将来的な後継者不足が課題になっている。今後、本県の復興の歩みを正確に伝え続けるためには、持続的に語り部が活動できる体制づくりが不可欠だと判断し、事業化を決めた。新年度一般会計当初予算案に関連費426万円を計上している。
内堀雅雄知事は14日の定例記者会見で、震災から12年目の重要課題は「風化」との考えを示した。その上で「風化の抑制なくして長い戦いを勝ち抜き、復興を成し遂げることはできない」と強調。県生涯学習課の担当者は「震災の教訓を後世に伝え、防災に関する学びを本県から発信していく」とした。
14日の2月定例県議会の企画環境委員会で県が示した。
- 美里で耕す第二の人生 浪江から避難、元SEの農家「恩返しを」
- 星降る農園、浪江のスターに 元外交官・高橋さん、移住し奔走
- 葛尾に国内最大エビ養殖場 7社出資のHANERU社、24年度出荷へ
- 白河・小峰城の北西エリア開放 石垣修復、4月9日に11年ぶり
- 【震災11年・備える力】災害語り部/記憶継承、若者の手で
- 豊間の伝承...防災紙芝居に いわきの団体制作、経験を次世代へ
- 郡山市、4小学校に「非常用備蓄品」配布 フードロスを削減へ
- 【震災11年・備える力】コロナ下/感染恐れ避難ためらわぬように
- 【震災11年・備える力】個別避難計画/「要支援者」を守る命綱
- 【震災11年・備える力】夜間避難/災害は時間を選ばない